2021年4月より活動を開始した、博展のZ世代の社員が中心となるサステナビリティ・アンバサダーが、SB2022横浜に参加。
全3回にわたるレポートの最終回の今回は「コミュニケーション・マーケティング編」です。様々な企業の中で、企業のサステナブルな取り組みと、ステークホルダー(利害関係者)とのより良い関係を繋ぐためのコミュニケーションの方法が模索されています。
Vol.03では、「#人」「#共感」「#共創」をキーワードに、それぞれのセッションを通して、企業とステークホルダーのコミュニケーションについてレポートします。
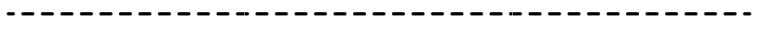
「サステナブル・ブランド国際会議 2022 横浜(SB2022横浜) 」とは
世界的なサステナビリティの潮流や取り組みを共有し、各業界の最前線で活躍する企業と情報交換できる日本最大規模のサステナビリティに関するコミュニティイベントです。
米SLM(サステナブル・ライフ・メディア社)社が展開する国際会議で12カ国(2020 年度)で開催され、来場者数はグローバルで1.3 万人を超える規模となっています。
日本国内では2017年から博展が展開し、第6回目となる今回は2022年2月24日~25日に、パシフィコ横浜ノースとオンライン配信のハイブリットで開催。
地球や社会をより健全でレジリエント(回復力のある)にするためのカギとなる『REGENERATION(リジェネレーション=再生)』をテーマに、200名を超えるスピーカー、のべ4,500人を超える参加者が集まり、ビジネスを変革し企業ブランドを再構築することで、地球上に住む人たち豊かになる環境や社会、経済をどうつくり出すことができるかを共に探求する場となりました。
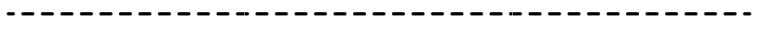
▼ライター紹介

渡邉
2020年新卒入社の2年目。
プランナー。主にtoC顧客企業の案件を担当。
サステナビリティについてはアンバサダーになってから興味が出てきました!

山口
2019年新卒入社の3年目。
営業。主にtoB顧客企業の展示会の案件を担当。
身近でできるサステナブルな行動を研究中!みなさんもマイボトルを使うところからスタートしませんか?

川津
2020年新卒入社の2年目。
プランナー。主にtoC顧客企業の案件を中心に担当。
サステナブルな活動を楽しみながら継続してやっていくことが今後の目標です!
目次
・「ファンづくり、コミュニティづくりから広げる共感マーケティング」
・「未来起点で未来を創る「Z世代✕100年企業」」
・「ストーリーで語る サステナビリティ 2022」
・まとめ
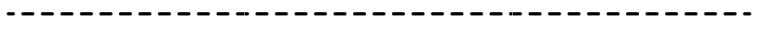
#1:ファンづくり、コミュニティづくりから広げる共感マーケティング
レポーター:渡邉

私は、博展ではBtoC向け商材を扱う企業のイベントに多く携わっており、その企画の中でクライアントとユーザーとの距離をいかに縮めるかに取り組むことが多いため、サステナビリティ的な側面も含めて、どのようにコミュニケーションを促進しているのかが気になり、今回本セッションを聴講しました。
本セミナーでは、一般社団法人NEWHERO 高島氏をファシリテーターに、石井造園(株) 石井氏、(株)ヤッホーブルイング 佐藤氏、日本生活共同組合連合会 峰村氏という業態も多種多様な3社がパネラーとして登壇。
いかにお客様へ共感を広げて企業との関係性を強くしていくかについて、事例のご紹介と共にお話されました。
(1)コミュニティの基本的な考え方
まずはコミュニティの考え方 / 前提について、ファシリテーターの高島氏から解説がありました。
・顧客→ファン→コミュニティの流れでコミュニティは変容する
・SNSは広く伝えることに特化し、コミュニティは深く伝えることに特化している
この前提を理解しておくことで、コミュニティ作りの一歩目を正しく踏み出せるのではないか、と高島氏は提言されています。
また、ヤッホーブルーイングの佐藤氏より、顧客の階層と感情の関係性についての解説もありました。「トライアル顧客→弱いリピート→リピート→ファン→伝道師」とだんだんと企業や製品との距離が縮まっていく中で、ファンとリピート層の間には「ミッションへの共感」があるかないかの違いがあるとのお話がありました。
「製品の良さを受け取るだけでなく、同じ方向を見れていること」は、お客様とより深い関係性を築くにあたって大切にするべき指針なのではないでしょうか。

(2)各企業ごとの取り組み紹介
①石井造園株式会社
年間20〜30回ほど実施される小さなCSR活動は徹底的に地域への還元が意識されています。これは1965年創業と長い歴史を持つ石井造園が、地域の理解あってこその企業活動ができているという思いから地域貢献を大切にしており、だからこそ活発な企業活動ができているそうです。
②株式会社ヤッホーブルーイング
EC事業を通して全国にいるユーザーと少しずつ繋がることでファンを増やし、工場見学ツアーから今後販売予定の製品についてファンと企業側が一緒に考える共創イベントまで多種多様なイベントを開催。また、SNSでは「宣伝する / 知る / 楽しむ」の3つのチャンネルを混ぜながら発信し、製品だけなくクラフトビールの世界も伝えることで、着実に新規メーカーファンを獲得しています。
③日本生活共同組合連合会
WEBの商品レビュー欄を会員が集える場所として設置。co-op自体がコミュニティの役割を果たしながら、商品レビュー欄にさらに小さいコミュニティを作ることで、エンゲージを高めています。一方、新規の人がコミュニティへ参入しやすいように、若い人向けにはSNSを通して広く周知する拡散的な活動も行う。
(3)コミュニティ作りのポイント
全社通して共通しているコミュニティ作りのポイントが2つあったので、ご紹介します。
■傾聴すること
現在のファン層だけでなく、今後ファンになり得る層も含めて「人の声を聞くことが大切だ」というお話がありました。佐藤氏からは「心掛けているのは、『接点(出会い)と沸点(ハマった瞬間)を知る』こと。」とのお話もあり、お客様の声に耳を傾けながらも、その心の動きを分析していくことは、より良いコミュニティを醸成していくために大切なムーブメントであると思いました。
■アクションを見える化させていくこと
WEB上で行われるコミュニケーションも含め、リアルでもWEBでも活動を記録として残して、見える化していくことが大事というお話がありました。石井造園の石井氏からは「見られていることで、襟を正すこともできる」というお話もあるなど、コミュニティへの還元以外に、自社への意識向上という面でも、大きく意味があると感じました。
<ライターの感想>
みなさん共通して大切にしていたのは「人」でした。
お話を聞く中で、全体像を俯瞰しながらコミュニティを設計するだけでは、深い関係性は築けず、当事者の声に耳を傾けることで初めてコミュニティに温度が宿っていくのだろうと感じました。コミュニティ全体を整理するだけでなく、時にはそこからはみ出るような人の声を大切にすることで、お客様がコンテンツにハマる瞬間=沸点を察知できるようになるのではないかと思います。
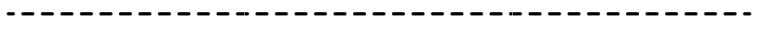
#2「未来起点で未来を創る「Z世代×100年企業」
レポーター:山口
昨今、「Z世代」という言葉を耳にすることが日常的になってきています。
しかし、その言葉は先駆者たちが、単に線引きをしているに過ぎないのかもしれません。持続可能な未来を築くためには、線引きは大きな障壁ともなりかねず、もはや「Z世代」の特性や個性を理解するばかりでなく、引き寄せ、巻き込み、活かすことが不可欠です。
本セッションでは、サステナブル・ブランド国際会議 D&Iプロデューサー 山岡氏をファシリテーターに、東京建物株式会社 青山氏、株式会社オンデザインパートナーズ 櫻井氏、NPO法人UMIBARI 伊達氏、サステナブルライフクリエイター/モデル 前本氏が登壇。

Z世代と100年企業によるコレクティブインパクト※の実例を通し、Z世代の力を知ると共に、先駆者たちの役割を踏まえ、共創のあるべき姿の探求を繰り広げました。
※コレクティブインパクトとは、様々なプレイヤーが共同して社会課題解決に取り組むための一つのスキームであり、共同の効果を最大化するための枠組みのことを指します。
<セッションサマリー>
(1)登壇者の共通する取り組みについて
-「um」について
六本木に人々が集まる「um(アム)」という場所ができました。
umは2つの意味があり、1つは「編みこむ」、もう1つは「umm…」と考えるときに使う言葉をかけています。
Z世代のアクターを起点に、世代やセクター、ジャンルの壁を超えた幅広い人々、またモノやコンセプトまでが入り混じり、自由な空間と時間の中で、より良い今日や未来のために「モヤモヤ」や「未完成」を編む場所が、今回の登壇者を軸に作られました。

各企業ごとの取り組み紹介
①東京建物株式会社
設立から126年。都市開発事業にて都内一等地での最明発事業の事業推進業務を担いながら、これからのまちづくりに必要な視点や、新しい商品企画などを検討中。
理想の街づくりは、企画・建設フェーズの段階から様々な人々と一緒になって共創しており、それは竣工した後も共創する人々とまちをアップデートすることと話されました。
②株式会社オンデザインパートナーズ(um空間デザイン)
「um」を共同設計している事務所。空間を作るだけでなく、街づくりにも寄与しています。空間を作って終わりではなく、環境など取り巻いている物を一緒に考えることをしているそうです。
③NPO法人UMIBARI(Z世アクター)
伊達氏が大学時代に立ち上げた海洋系プラスチックごみ問題の解決を目指すNPO法人。
合同会社を立ち上げたり、マルチにサステナブル問題に取り組んでいるそうです。
④サステナブルライフクリエイター(Z世アクター)
前本氏は、環境問題を学んでいくうちに、気候変動の問題の深刻さを知ったそうです。
自分が草の根でできることをテーマに、YouTubeやインスタグラムで発信します。
(2)umについてのディスカッション
空間設計について、興味深い考え方がありました。知らない人たちが、円滑にコミュニケーションをとったり、何気ない会話を始めたりするためには、いろんな視線の「高さ」を設けた方がいいとのことです。
実際に登壇者で作り上げた「um」のオフィスでは、様々な高さの椅子やジャングルジムが置かれています。同じ高さの椅子だけの空間と、いろんな種類の椅子(高い椅子、低い椅子、カラフルな椅子)がある空間だと、後者の方がコミュニケーションの幅が広がるとオンデザインパートナーズの櫻井氏が話されていました。視線の高さだけでなく、いろんな椅子の色が並んでいると多様性が生まれ、いろんなIDEAがでるそうです。
世界には様々な人がいて、椅子一つとっても相性が異なり、自分に合うものを見つけたときにより普段に近い自分を出すことができて意見を言い合える場になるのかなと感じました。
<ライターの感想>
特に自分の中で印象に残ったのは、「予想を裏切ることは価値になる」というUMIBARIの伊達氏の言葉です。
予想外のことが起きると「失敗になっちゃったね」と多くの人は感じますが、「検証」というフェーズに「共創」をあてていくことで、伊達氏は予想外なことは検証材料として持ち帰ることができ、スキームが出来上がっている感触が、今後の新たなプロセスとして加えられると話されていました。
普段、私は企業の展示会出展サポートをメインに担当しており、通常は展示会の会期までにブースのレイアウトをしっかり作り上げた状態で当日を迎えていますが、現地会場で初めて周りのブースの様子や人の流れの状況を知ることもあります。そのような、予想をしていなかった状態になった時、失敗してしまったと思うのではなく、施工中、会期中も「検証」をし続けて、クライアントと共創する事が重要だと感じました。
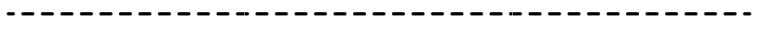
#3「ストーリーで語る サステナビリティ 2022」
レポーター:川津
「ストーリーで語るサステナビリティ」はこれまでも何度か同じタイトルで開催されている、SBでも人気のテーマの1つです。
会社のサステナビリティへの取り組みを社内外に共有していくにあたって、取り組みの内容はもちろん、「ストーリーで語る」ことはとても重要になってきています。このセミナーでは、登壇されている企業の実例を交えてディスカッションしながら、その「伝え方」についての考えを深めていきました。
サステナブル・ブランド国際会議 サステナビリティ・プロデューサー/株式会社レスポンスアビリティ 足立氏をファシリテーターに、株式会社 LIFULL 井上氏、パーソルホールディングス株式会社 美濃氏、株式会社 日立製作所 佐藤氏、株式会社オカムラ 佐藤氏が登壇。

私は、普段プランナーとしてお仕事をさせていただく中で、自分の考えをお客様や社会にどう伝えるか、ということを考えることが多いことから、そのヒントを見つけたい思い、今回このセッションを聴講しました。
<セミナーサマリー>
(1)各企業ごとの取り組み紹介
■ 株式会社オカムラ 上席執行役員 コーポレート担当 佐藤 喜一
「“人が想い、場を創る。”オカムラの取り組みについて」
■ 株式会社 日立製作所 サステナビリティ推進本部 佐藤 亜紀
「日立の社会イノベーション事業について」
■ パーソルホールディングス株式会社 執行役員 美濃 啓貴
「グループビジョン“はたらいて、笑おう。”の実現に向けて」
■ 株式会社 LIFULL 代表取締役社長 井上 高志
「社会課題を解決しながら利益を上げ続ける企業活動について」
(2)それぞれの発表を踏まえてディスカッション
(3)「これからサステナビリティをどのように語っていくか、実行していくか」という問いに対してそれぞれの意見発表
内容トピックス
①パーソルホールディングス株式会社の企業調査について
「はたらいて、笑おう。」グローバル調査 https://www.persol-group.co.jp/sustainability/well-being/worlddata/
パーソルホールディングスのビジョンである「はたらいて、笑おう。」を生きたものにするためには、どのようにKPIを定めていくのがいいか考えたそうです。その結果、それを測定する方法の1つとしてグローバル調査を行いました。
「働く」ということに対して、個人が主観的に感じる価値を3つの問いを通して世界の人々に調査していて、それぞれの国の文化やそれに基づく考え方が結果に現れているところが興味深かったです。
このグローバル調査の結果を、深め・広げることでパーソルに関わる社員やお客様の「はたらいて、笑おう。」を実現し、ゆくゆくは全世界で「はたらいて、笑おう。」 の実現を目指すと美濃氏は話されていました。
②LIFULLのコーポレートCMについて
LIFULL 企業CM 「しなきゃ、なんてない。2021年」篇
LIFULLがコーポレートメッセージである「あらゆるLIFEを、FULLに。」のもと、既成概念の枠を超え、多様な人の、多様な生き方をサポートしたいという想いから生まれたメッセージを伝えるCM。
大きな反響を呼び、LIFULLの認知度を上げるきっかけとなったこのCMは、LIFULLの主要サービスである不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」のサービス単体を訴求するCMと比べて、コーポレートCMの方がサービスの利用移行率が高まるという効果を生み出したというお話が印象的でした。
この結果を受けて、井上氏は、世の中の人が企業に対して“共感”を大切にしているということを改めて感じたとおっしゃっています。事業それぞれはもちろん、会社全体の取り組みを一気通貫で真摯に取り組んでいることが世の中の人の共感を呼んでいる。また、企業は想像しているビジョンに対してバックキャスティングで事業に取り組んでいるが、その事業だけを見せるのではなく、ビジョンをお客様にも見せていくことが、企業のイメージをつくるきっかけになると話されていました。
<ライターの感想>
特に自分の中で印象に残ったのは、「社員一人ひとりが”社会に貢献できていること”を実感して仕事をできていることが、結果として良い社会インパクトに繋がっていく」というオカムラの佐藤氏の言葉です。
毎日働く中で、目の前のことに精一杯でそれが社会にどのような影響を及ぼしているのか、どう貢献できているのかまで考えきれていなかったことにこのお話を聞いて、改めて気づかされました。「働く」ということに対して、条件やその内容だけでなく、その仕事がどのように社会に貢献できるのか、という視点で考えることができたら、もっとやりたいことの幅が広がりそうだと感じました。
また、仕事を通して社会に貢献できていることを実感するためには、まず自分の会社の理念や仕事に対する考え方を理解し、共感することが必要不可欠であるため、社員側からは理解しようとする姿勢、会社側からは社員に共感してもらうための伝え方が重要だと改めて思いました。
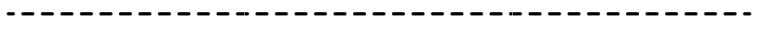
■まとめ
今回3つのセクションごとにレポートを作成しましたが、共通して「人」を大切にしていました。一緒に空間を作り上げる「仲間」の意見を尊重したり、話の軸からはみ出るような「人」の声を大切にしたり、「社員」の意見を聞いて働き方改革したりと相手のアクションを受け入れる大切さを学びました。人が発信するアイディアを否定するのではなく、耳を傾け、誰もが自由に発信できる世の中を目指したいです。
<SDアンバサダーとしての活動と今回SB横浜そのものに参加した感想>
・山口:サステナビリティから考える世界共通の問題をアンバサダーにならなかったら考えることもできなかったのでとても良い経験となりました。少しでも多くの人が環境問題に向き合い、進んでアクションしてもらえるように活動していきたいです。
・川津:“サステナブル”という共通テーマが既にあるので、事業領域や年齢に関わらず、
同じ目線で話すことができ、取り組みについての意見交換ができたことがとてもよい経験になりました。
・渡邉:それぞれブランディングやコミュニティ作りなどテーマの違いはある中でも、個人(お客様や社員など全て)の行動をを引き出すようなアクションが、活動の話をポジティブに広げていくためには大切だということを改めて実感しました。


